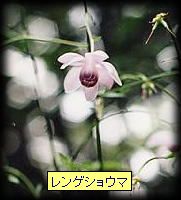◇山野の植物◇
低地帯から高山帯までの311種の植物を紹介しま
す。
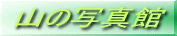
◇山岳地形や植生について◇
日本の山岳地形や植生の特徴や面白さをお伝えします。
- 雨飾(あまかざり)山の地形や植生
多量の雪が流れ落ち、山の斜面を削り取ってできた地形(アバランチ シュート)と植生の面白さを紹介します。
- 周氷河地形
南アルプスの小赤石岳山腹に見られた「ソリフラクション・ロウブ」、 中央アルプスの木曽駒ケ岳山頂部の「階状土」、及び群馬県北西部にある本白根山の鏡池で見られる大型「亀甲(きっこう)状土」を紹介します。
- 二重山稜
北アルプス西鎌尾根にある樅沢(もみさわ)岳(2755m)から北に 向かって2519.2mのピークまで伸びる稜線に沿って観察されました。
- カー
ル地形
氷河によって削られた地形です。北アルプスの薬師岳、立山、笠岳、黒 部五郎岳、南アルプスの赤石岳、千丈ケ岳のものを紹介します。
- 花
崗岩(かこうがん)のトアをもつ山
奥秩父の金峰山・瑞垣(みずがき)山及びその周辺の山、及び南アルプ スの北にある日向(ひなた)山で観察されました。
- 蛇紋岩(じゃもんがん)の山
尾瀬の至仏(しぶつ)山が代表各
- 石灰岩(せっかいがん)の山
鈴鹿山脈北部の御池岳・藤原岳
掲載されている写真は全て著者が撮影したものです。教育目的以外での使用はお断り致します。
使用する場合は、「掲示板」でご連絡下さい。
使用する場合は、「掲示板」でご連絡下さい。
(Copyrights All Reserved)
 2014年9月23日
2014年9月23日シオガマギク属・コゴメグサ属をハマウツボ科に移し、クワガタソウ属はオオバコ科に移しました。また、ユリ科シュロソウ属をシュロソウ科とし、従来ユリ科ツクバネソウ属に分類されていたキヌガサソウはシュロソウ科キヌガサソウ属に移しました。思ったより早く改訂作業を終了できました。
 2014年9月21日
2014年9月21日ヨツバシオガマやエゾシオガマなどのシオガマギク属とミヤマコゴメグサなどのコゴメグサ属は、従来はゴマノハグサ科に分類されていましたが、近年の系統学的な研究からハマウツボ科に移動、またオオイヌノフグリなどはオオバコ科に分類されるようになったそうです。(2014年9月神戸大学の小菅先生からご指摘いただきました。)本HPでは改編作業が間に合わず、しばらく旧分類のまま掲載させて頂きます。御了承下さい。
 2011年5月25日
2011年5月25日ここに掲載しきれない野草がだいぶ増えてきたのですが、それをこのサイトの形式に従って紹介するには少々時間がかかります。そこで旅先などで出会った植物を迅速にかつ気軽に紹介するために「山野草つれづれ日記」というサイトをCMSのMagic3を用いてつくりました。こちらもぜひご覧ください。
 2009年10月3日
2009年10月3日シラヒゲソウ、オミナエシ、オトコエシ、イヌゴマ、カワラナデシコ、ユウスゲ、ノカンゾウ、キンミズヒキ、ダイコンソウ、イチヤクソウ、ミゾホオズキの11種を追加し、タチフウロ、ゲンノショウコ、ヨツバヒヨドリのページを改訂しました。掲載種数は311種となりました。
 2009年8月17日
2009年8月17日「情報教育とOSS」を「山野の植物と山岳地形」から切り離して、「Linux の活用をめざして」と いうサイトを立ち上げました。こちらもご覧下さい。
 2009年5月31日
2009年5月31日ジ ロボウエンゴサク、センボンヤリ、ノ ジスミレ、キ ツネノボタン、ハ ナミョウガ、トウバナの 6種を加え、ア リアケスミレのページを更新しました。結果300種の植物を紹介することになりました。
 2009年5月10日
2009年5月10日ア カヒダボタン、ナガハシスミレ、ス ミレサイシン、オ オイワカガミ、ニオイタチツボスミレ、ム ラサキケマンの6種を加え、ネコノメソウの仲間とエンゴサクの仲間については削除・訂正及び写真改訂等の作業を行いました。また他に も数種のものについて写真及び文章の改訂作業を行い、結果294種の植物を紹介することになりました。
 2009年5月6日
2009年5月6日「カタクリの写真館」を新設しました。16枚の写真のスライドショーになっています。
 2008年10月25
日
2008年10月25
日モ ウセンゴケ、イワブ クロ、キタヨツバシオガマ、ミ ヤマオトコヨモギ、ミ ヤマキンポウゲ、オオレイジンソウの6種を追加しました。
 2008年9月20日
2008年9月20日今まで撮りためた山の写真を「山の写真館」として公開しました。
 2008年8月19日
2008年8月19日firefox3.0版で表示がトップページの表示が乱れていたのを改善しました。
 2008年7月6日
2008年7月6日新たにコアジサイ、ヒメレンゲ、スズランを加え、全 282種になりました。キンランの ページも改訂しました。
 2008年6月14日
2008年6月14日南信州の治部坂高原でスズランが見頃でした。
 2008年5月10日
2008年5月10日連休最後の日、雨生山(静岡県と愛知県の県境にある標高313mの山)に行きました。林床部の所々にキンランが咲いていました。
 2008年3月31日
2008年3月31日トップページを大幅リニューアル

鈴蘭高原で、もう使われなくなったような別荘の庭に、ひっそりと咲いていました。